講座紹介一覧
検索メニューは、2種類あります。
ピックアップ講座を紹介します。 太陽熱で水を温める実験を通して、太陽熱エネルギーの力を実感する。 森林のはたらき(機能)を知ることで、森林に親しみを持ち、保全の意識を高める。 温度上昇測定実験を通して、私たちにできる温暖化防止策を考える。 牛乳パックを使ったはがき作りを通して、リサイクルの必要性について学ぶ。 「筆立て」「ティッシュ入れ」「エコバッグ作り(新聞紙)」にも対応。 身近に見られる野鳥を観察し、野鳥に親しもう! 「暑い」「涼しい」と感じる原因を探し、快適に過ごす工夫を考える。 生きものの個性とそのつながりから私たちが受ける恩恵について学ぶ。 ソーラークッカー実験を通して、太陽熱エネルギーについて学ぶ。 身近な水の分析を通して、周辺の環境を知る。 生きもののつながりについて、水中の微生物観察から学ぶ。 五感を使って校庭や学校周辺でみられる樹木を観察する。 ごみ収集車の体験を通して、リサイクルについて学ぶ。 フードマイレージについて知り、食材の選び方や、地球温暖化との関係を学ぶ。 給食の食材を取り上げ、食べ物を大切にする気持ちを育む。 分別ゲームを通して、ごみの分別方法や雑紙について学ぶ。 アマモ場観察を通して、浜名湖の恵みを知る。 買い物ゲームを通して、地球にやさしい視点から商品の選び方を学ぶ。 「寒い」「暖かい」と感じる原因を探し、快適に過ごす工夫を考える。 園庭や校庭でダンゴムシを探し、いきものマップを作ってその生態を知る。 家庭のエネルギー消費量を知り、具体的な省エネ方法を学ぶ。① ピックアップ検索
(試行錯誤しながら、講座を検索するメニューです)
※赤丸の数字は、講座件数を表示しています。
② 詳細検索
(カテゴリーや対象が決まっている方が検索するメニューです)【講座No.103】太陽熱はあったかい ~太陽で水を温めよう~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.102】森林はみんなの宝物 ~森林の価値を知ろう~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。。
【講座No.101】あたたまる地球 ~目指せ!エコマスター~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.100】浜松リサイクル工房 ~はがき作り編~

講座時間
90分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.99】鳥トリドリな世界 ~どこでも楽しい♪バードウォッチング~

講座時間
90分
実施場所
フィールドまたは校庭
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.98】環境に“E”生活 ~快適さを求めて・夏編~

講座時間
90分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.96】いきものと私たちとのかかわり ~自然からの贈りもの~

講座時間
50分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.95】太陽はトモダチ ~太陽の力で調理しよう~

講座時間
90分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.94】水を読む ~水を分析しよう~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
このプログラムは学校向けです。
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。【講座No.93】いきものリレー ~最初はだぁれ?~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
このプログラムは学校向けです。
プランクトンは5~9月が観察時期です。
申込みは直接環境政策課になります。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。【講座No.92】この木しってる? ~身近な樹木観察~

講座時間
90分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.91】ごみはトラベラー ~ゴミ収集車がやってくる~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
このプログラムは学校向けです。
月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌日)は、実施できません。
申込みは直接環境政策課になります。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.90】食材はトラベラー ~産地から食卓まで~
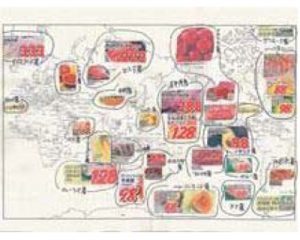
講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.89】すごいぞ!給食 ~「みーんな、いただきます!」~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.88】今日から我が家の分別係 ~ごみ分別ゲーム~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.85】海のゆりかご探検 ~浜名湖アマモ場観察~

講座時間
半日
実施場所
弁天島海浜公園(いかり瀬)
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
渡船料等が必要となります。
駐車場は渚園又は弁天島海浜公園(いかり瀬)有料駐車場をご利用ください。
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。【講座No.84】環境に“E”お買い物

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.83】環境に“E”生活 ~快適さを求めて・冬編~

講座時間
90分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。
【講座No.81】いきものかくれんぼ ~ダンゴムシを探せ~

講座時間
45分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
ダンゴムシは4~9月が観察時期です。
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。【講座No.80】あなたにもできる「省エネ」のコツ ~小さな工夫で大きな効果~

講座時間
50分
実施場所
学校等
協力団体・人材
浜松市環境政策課Eスイッチ
備考
浜松市環境政策課へ直接お申込みください。お申込み方法や講座内容、準備物は下記リンクからご確認ください。